「iDeCoは60歳まで解約できないけど、加入者が死亡したらどうなるの?」
「死亡一時金を受け取るとき、税金はかかるの?」など、iDeCo加入者が死亡した場合の手続きや資産の受け取りについて疑問を持つ方は多いでしょう。
本記事では、iDeCo加入者が死亡した際に必要な手続きや資産の受取人、税金の扱いについて詳しく解説します。
遺族がスムーズに手続きを進められるよう、必要な情報をすべて網羅していますので、最後までご覧ください。
iDeCo加入者の死亡時は遺族が資産を受け取れる
iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者が死亡した際、その口座内の資産は売却され、配当金も含めた全額が死亡一時金として遺族に支払われます。
支払いは現金一括で行われ、年金形式での支払いはありません。
死亡一時金の受け取り方
死亡一時金は、iDeCo加入者が死亡した場合、その遺族が一括で受け取ることができます。
これは、年金形式での支払いがないため、一度に全額を受け取ることになります。
iDeCo加入者の死亡時に受け取る死亡一時金の税金
死亡から3年以内に支給される場合は相続税の課税対象
死亡一時金は、死亡から3年以内に支給される場合、相続税の課税対象となります。
この場合、500万円×法定相続人の数までが非課税となり、一定額以下であれば相続税の負担が軽減されます。
死亡から3年以上かつ5年以内に支給される場合は一時所得の課税対象
死亡から3年以上5年以内に支給される場合は、「一時所得」として所得税の対象となります。
受け取った一時所得はその年の所得税の対象となり、金額に応じて課税されます。
死亡から5年以上経過すると死亡一時金を受け取れない
死亡から5年以上が経過した場合、死亡一時金の受け取りはできません。
遺族が死亡一時金を受け取るためには、死亡後5年以内に手続きを行う必要があります。
iDeCo加入者の死亡時に資産を受け取るのは誰?
死亡一時金の受け取り順位
iDeCoの死亡一時金の受け取り順位は以下の通りです。
- 配偶者
- 加入者等の収入によって生計を維持していた親族
- 加入者等の収入によって生計を維持していたその他の親族
- その他の親族
同順位に複数の対象者がいる場合は、資産が等分されます。
事前に受取人を指定することも可能
加入者が事前に受取人を指定することも可能です。指定可能な受取人は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限られます。
iDeCo加入者の死亡時に遺族や受取人が必要な手続き
遺族や受取人は、「裁定請求」という手続きを行う必要があります。具体的な手順は以下の通りです。
- 必要書類の取得
- 取得する書類には、金融機関の加入者死亡届、裁定請求書、受取人のマイナンバーカード(またはマイナンバーが分かる書類)、受取人の印鑑証明書が含まれます。また、受け取り順位や人数に応じた書類も用意します。
- 書類の記入と提出
- 取得した書類に必要事項を記入し、裁定請求に必要な書類とともに記録関連運営管理機関に提出します。
- 裁定の完了と支払い
- 提出された書類をもとに記録関連運営管理機関が裁定を行い、裁定が完了すると指定された口座に死亡一時金が振り込まれます。
生前に準備しておくべきこと
生前に適切な情報提供を行い、家族にiDeCoの存在や必要な手続きについて説明しておくことが重要です。また、万一の事態に備えて家族にiDeCoのコールセンターの番号を知らせておくと安心です。
iDeCo加入者の死亡時に関するよくある質問
Q: iDeCoで受け取れる死亡一時金の金額は?
A: 加入者の運用年数や運用状況により異なりますが、口座内の全資産が対象です。
Q: iDeCo加入者の死亡時に楽天証券で必要な手続きは?
A: カスタマーサービスセンターへ連絡し、必要な手続きの案内を受けてください。
Q: iDeCo加入者の死亡時に死亡一時金を受け取る際、税金は発生する?
A: 支給タイミングによって相続税または一時所得として課税されます。
Q: SBI証券でiDeCoの死亡一時金の受取人指定をする方法は?
A: 「死亡一時金受取人指定申込書」を提出し、手続きを行います。
まとめ
iDeCo加入者が死亡した場合の手続きや死亡一時金の受け取りについて解説しました。
適切な手続きを行うことで、遺族が資産をスムーズに受け取ることができます。事前の準備をしっかり行い、万一の事態に備えましょう。
この記事を参考にして、iDeCoの死亡時の手続きをスムーズに進めましょう。
またiDeCoに関しては下記記事にもまとめがありますので、ぜひ参考にしてください!
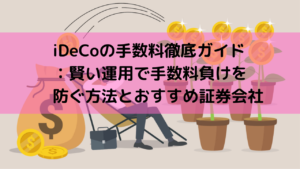
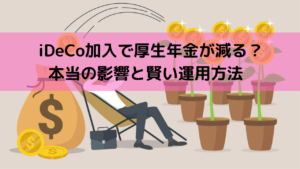
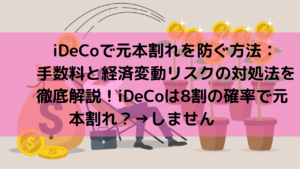
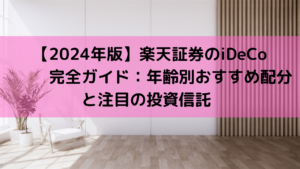
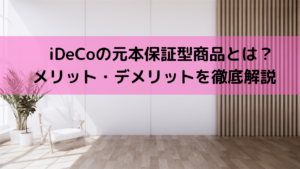



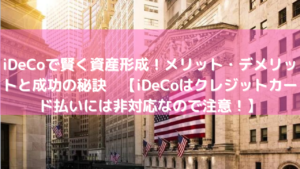
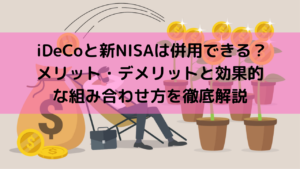
コメント